【同人再録】さっきまで滅茶苦茶SEXしてた。(バク獏・盗獏)
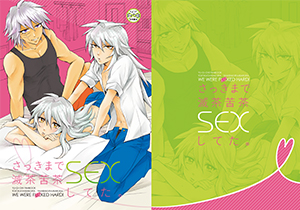
発行: 2014/10/12
「 さっきまで滅茶苦茶SEXしてた。 」
そのまんま事後本。キリサメさんと合同誌、ゲストにみゆさんと半田96さんをお招きしております!再録分の西尾SSはわりとギャグめの3Pです。
表紙・漫画:キリサメ様
小説:描き下ろし
ゲスト:半田96様・みゆ様
夕方だというのに、窓の内側は冬の朝のように曇っていた。
スモークを貼った車の窓の如く、あちらとこちらの繋がりは断たれている。行楽日和の日曜日、外の大通りはデート帰りの心地よい疲れに良い顔で愚痴を言いながら歩くカップルやまだはしゃぎ足りない家族連れの声と車の排気音で明るくも賑やかだ。
それに引き替えこちら側――締め切った六畳部屋は怠惰極まりない。
狭いシングルベッドに高校生二名と年齢不詳の男が一名、計三人。
曇り窓の原因である熱く湿った二酸化炭素を無秩序に吐き出しつつ、ぐったりと折り重なっているのだから。
「……あっつ」
これで三回目になる文句を、ベッドの真ん中の盗賊王を斜めの敷布団にした獏良が呟く。
「だったら退けよ、暑苦しい」
傾いた獏良の足を枕にしたバクラが、目も開かずにそう述べる。
「オレ様は構わねえけど、あんまくっついてっとまた勃つぜ」
湿ったシーツが背中で丸まっているのも気にしない盗賊王が、この中で一番の体力自慢だった。少しばかりまだ余裕のある表情で、しかし動く気がないのは犬猿の仲のバクラの足が顔近くに伸びていても退かさないことから伺える。
「誰だよ、3Pしようとか言いやがったのはよ……」
うつ伏せにバクラが呻くと生温かい息が獏良のくるぶしに当たる。きもちわるい、と口をとがらせても、除けも止めもしなかった。
誰が発端かと問われたなら、それすら全員、記憶の外にあった。
吹っかけてきたのは盗賊王であった気もするし、戯れに気が乗ったのはバクラだったかもしれない。嫌だと言いながらいっとうしどけない声を出していたのは獏良だったか。ともかく全員が全員、犯人で共犯で被害者だった。
流れのままに脱いだか脱がされたかすら定かではないシャツやジーンズが哀れシーツと一体化し、肌は互いの境界線を無くしている。普段は寝具と大差ない獏良の肌の色さえ内側から熱の色を映してほの赤く、それはやけに扇情的だったのだけれども如何せん、煽られても起き上がる気がしない。
けれど揃って、もう一戦くらいは致したい気分ではあるわけで。
「おい宿主、お前一番働いてねえだろ、もうひと踏ん張りしやがれ」
「そりゃ同意見だ。了、頑張れ」
こっちは腰が痛むのだ、と、違う顔で元はひとつの二人は横柄な様子で獏良に持ちかけた。
汗で頬に髪を纏わせた獏良はそれだけでいかにも危うげで、壊れやすいものを壊すことを好む二人にはことさら美味そうに見える。折れそうにもろい腰が乗った腹を盗賊王が軽くゆすると、不穏な揺れに獏良はくっと眉をひそめた。そうするといっそう、雄共の官能を誘うことは本人の自覚の外にある。
だが、湿った唇が吐き出した言葉は二人が思ったより辛辣だった。
「突っ込む側の人は気楽でいいよね。どれだけ負担がかかるか教えてあげようか」
ちら、と、視線を動かした先には、獏良が散らかしたままの勉強机。極太、と、その太さを物語る威圧的なロゴを晒した油性ペンが赤と黒と転がっているのを見つけて、バクラは舌打ち、盗賊王はうえっとあからさまに萎えた顔だ。自分たちはそれ以上のシロモノを自前で使っている癖に、される側に立たされかけるととたんにこうである。獏良がふんと鼻を鳴らすのも当然のことであった。
「疲れ具合で言うならボクが一番ひどいんだからね。顎も下の方もジンジンする。ものが食べられなくなったらどうしてくれるんだ」
恨みがましげな声音に、盗賊王はどこ吹く風で口の端を持ち上げてみせた。ちょいちょい、と、顎の先でバクラを指して、
「そしたらやさしーく介護してやるよ、ソイツがな」
「冗談じゃねえ、誰がやるか」
「大事なヤドヌシサマなんだろ? あんま冷たくすると嫌われちまうぜ」
「てめえもな」
「オレ様は愛されてるからよォ、なあ了?」
「どっちもどっち」
はぁあ。
と、ため息をついたところで、ぐう。
三人折り重なったちょうど真ん中で、腹の音が鳴いた。
「……オイ誰だよ、色気のねえ」
「ボクじゃないよ、おっきいバクラじゃないの?」
「そういや腹減ったな」
空腹に腹をさするにも上に乗った獏良が邪魔で、それもできない。盗賊王はふんすと鼻息を漏らし、代わりにくしゃくしゃと獏良の髪を掻き回した。
「そろそろ飯にしねえ? 昼から何も食ってねえぜ」
「昼と夕飯の間は普通何も食わねえだろ……」
「ったく、そんなだからいつまでもモヤシなんだろテメエらは。
おう了、何か作れよ。肉食いてえ肉」
くしゃくしゃと掻き回した手で、今度はぽんぽん。
言うとおりにすることが当然という仕草で促された獏良はむっ、と頬を膨らませ、次いでぷいと向こうを向いた。
「ヤだ」
「あァ? 何でだよ」
「ボクがやって当然みたいな言い方するから、嫌。だいたいおっきいバクラはいつもそうだよ、たまには自分でやりなよ」
「オレ様に料理しろってか? は、そいつは御免だな」
「ボク好きだよ? おっきいバクラが作るよくわかんないシチューみたいなごった煮。お夕飯、あれがいいなあ」
相手を褒めることで自分の作業を減らす手管も、獏良はここ最近で習得しつつあった。三人暮らしも慣れてきて、何をどうすれば盗賊王を乗り気にさせられるのかも大分解って居る。以前はどうだったか獏良には定かではないが、今の彼は基本的には気のいい男だ。そして大抵の成人男性がそうであるように、おだてが好きで褒められることに弱い。
女性のように手練手管を駆使することに、獏良にも抵抗はあったがそれも最初の内だけ。結果的に楽ができることが分かった今、率先して使っていく所存である。特にこんな、疲れ切った事後には。
しかし、疲労度はともかく動きたくない感情度では、獏良も盗賊王もとんとんであった。盗賊王は一瞬気をよくした表情を浮かべたが、すぐにうへえ、と口を曲げ、
「作るとかするわけねえだろ、大体肉がいいっつってんのに汁物はねえよ。肉。分厚い奴な。牛か羊だ」
「冷凍庫に牛ロースあるよ。かじれば?」
「生かよ、さすがの俺サマも腹壊すわ」
「だいじょうぶだよ、ほらこんなに筋肉ついてるし」
「いやそれ関係ねえから」
くう。
とりとめない会話の間で、二度目の腹が鳴る。可愛らしい音は獏良のものだった。空腹が過ぎて痛みを伴う腹の音だったらしく、うううと短く唸った獏良は、盗賊王の上で身体をよじる。
「いたい。お腹いたい」
「おら、だから飯作った方が良いんだって」
「駄目。どうしても食べたいなら一人で食べて」
「あ?」
「七時から九時の間に、おとりよせスイーツが来るから。絶品生クリームのとろふわシュークリーム三個セットの為にボクの胃袋はからっぽにしておくんだよ」
そもそも腹を空かせたいからこそ、短時間で消費が可能な運動――という名のセックス大会に参加したようなものなのだ、と、堪える表情で獏良は言った。なんだそれと盗賊王は呆れるが、病的なシュークリーム好きは良く知っているのでそれ以上は言及しない彼である。
盗賊王はぎゅっと眉を寄せ、それから故意に甘やかす動きでもって獏良の頬を撫ぜた。盗賊王の扱い方を心得ている獏良だが、その逆もしかり、だ。甘やかし、とろとろにしてやると獏良は大抵なあなあになって言うことを聞く。単純なのだと認識しているが、本人もまた同じである。
「なァ了、あとで好きなだけ気持ちよくしてやるからよ。大人しく言うとおりにしてくれや。夜ンなってから手酷く苛められたかねえだろ?」
紫の瞳は薄く伏せ、視線は甘く、されど口元には獰猛な笑み。見事な甘やかしと脅しの二刀流――
だったが、今日の獏良は頑なだった。
「ボクの身体は深刻な糖分不足に陥っているから、どんなふうにお願いしてもだめ」
「ンだよ、本当に苛めんぜ?」
「やだけど駄目。ていうか無理。ガソリンない。ガス欠。ライフゼロ。山札も手札もないの」
「零だったら死んじまうじゃねえか」
「じゃあ残り一でいい。とにかく無理ったら無理――」
と、そこで獏良はふと気が付いた。
先ほどからバクラが一言も喋っていない。
「バクラ?」
億劫な身体を無理しいしい、首を持ち上げて足の方を疑うと、獏良の膝を枕にうつぶせていたバクラがそのままの体勢でベッドに沈んでいた。両手を投げ出し、まさしく行き倒れといった風体で、ボクサーパンツ一丁で倒れ伏している。よく見るとかろうじて背中が上下しているので、死んではいないらしかった。
「バクラ? だいじょぶ?」
「何だ、完璧にへばっちまったのかよ」
左右からつんつん、と、爪先で突かれてもバクラは動かない。ただ首だけがギギギと横を向き、二人へ向けた瞳は死にかけの蝋燭のように力なく濁っていた。訝しげな獏良へ一言、バクラは呟く。
「血が足りねえ……」
「うわ、なんか聞き覚えがあるようなないような台詞」
見れば、バクラの顔は白くなりつつあった。先ほどまでは激しい情交の跡を色濃く残し、不健康ながらも血の色を透かしていたというのに名残もない。
どうやら獏良と盗賊王の食事談義の間に体調が崩れて行ったらしい。連戦に次ぐ連戦、そして意地でもプレイのイニシアチブを譲らなかったバクラである、当然の結果ではあった。ついでに言えば普段の偏った食生活も、貧血の一端を担っていることは間違いない。
「だらしねえな、普段から米も肉も食わねえからそんなことになんだよ」
「朝ごはんは食べた方が良いって言ったのに、言うこと聞かないから」
好き放題に言う二人にバクラは言いかえす気力もない。遠く長く響き続ける耳鳴りが邪魔でそもそもあまり聞こえていない。手足の感覚が遠のき、すうっと冷たくなっていく。後ろへ引っ張られ際限なく落下していく錯覚は、元闇そのものであっても気持ちの良いものではなかった。
というか肉体なんてものがあるからこんなことになるのだ、これなら千年リングの中にいた頃の方がずっとずっとマシだった。肉体よりも貧血の不快感の方が重たいと切実に思うバクラは実に世俗に染まっている。これでは闇のそのもの、の後に括弧笑い括弧閉じ、とつけられてしまっても文句を言えない。
「了、ここに肉を欲してる奴が二人もいるんだぜ? いい加減折れてくれたっていいじゃねえか」
「バクラ巻き込んで自分の欲求通そうとするの、格好悪い」
「そんなんじゃねえよ、純粋な親切で言ってやってんだって」
「純粋な親切をする人は、そんな風にニヤニヤしない」
「うるせえだまれ、頭に響く……」
まるで二日酔いのパパの如き言葉に、獏良と盗賊王は顔を見合わせた。これは本当にまずいのではないか、いや、多分わりと重症である。
きっと起きて、汗を拭いて、正しい姿で寝た方が良い。頭を低くして清潔なベッドで横になり、適切な栄養を取ればすぐに良くなる。分かって居る。分かって居るが、どうにもこうにも、動きたくないのが本音であった。
「なあ、テメエも肉食いてえだろ? 血が足りねえなら覿面だぜ? 了に言ってやれよ」
仲間に引き込みたい盗賊王は弱っているのを良いことに、己の陣営にバクラを引き込もうとする。
しかしバクラは力ない青い瞳を不快に歪め、一言、
「……ンなもたれるモン食いたくねえ」
獏良も半分心配で、半分楽がしたい為に言う。
「レバーとかのがいいんじゃない? うちにはないから、夕飯、定食屋さんか何かのデリバリーにしてあげようか」
またまたしかし、バクラはぐいと反対側に頭を向け、
「……生臭ぇモンなんぞ見ただけで吐く」
「「我儘言うな!」」
二人そろってのお叱りだった。
「グダグダグダグダ、月に一回機嫌悪くなる女かテメエは!」
「そんなにいやなら冷蔵庫のホウレンソウでも齧ってなよ! 大体そうなってるのは不摂生なくせにやたらがっついたお前の自業自得なんだからね、心配して損した!」
時として怒りは疲労を凌駕する。いわゆるおこ状態となった了は一歩も動かしたくないはずの足でバクラの頭を小突き、八つ当たりに盗賊王の胸に頭突きした。不意打ちに、おぐぇ、と表現しづらい音をたて、盗賊王がのけぞる。
「もうさあ、いっそ全員で同時に起き上がってみるとかどうかな! いつまでもこんなことしててもどうしようもないじゃないか! シュークリーム来ないし!」
「七時っつったの宿主だろ……」
「それが最短だったんだよ!」
貧血でも冷たいツッコミを忘れないバクラだが、腹立ちが限界突破している獏良には通用しない。
「誰か一人を生贄にしようとするからこうなるんだよ! 皆で起きれば怖くない!」
「いかにも日本人らしい発言だなァ」
「郷に入っては郷に従うものだよ! 古いエジプトの人は素直に言うこと聞く! バクラも少しだけ頑張る!」
という獏良のご命令に、二人はしぶしぶ、ハイともうぇーいともつかない気の抜けた返事をした。目を三角にした獏良に逆らうとろくな事がないと、身を以て理解しきっているのである。家事の全般を担っている獏良の機嫌を損ね、天岩戸に引きこもられるようなことがあっては、残った二人はまともな生活をおくれなくなる。こんなことならば少しくらい手伝いなどして弱みを握らせ無くしておけばよかった。後悔はいつも苦い。
「せーの、で起きるんだからね? いいね?」
音頭を取る獏良が、息を吸い、やけくその元気をふるってせえの、と言う。
ぱん、と、湿った部屋を叱咤する音で手を叩き――
「はいっ!」
そして、誰も起きなかった。
「……」
「……」
「……」
「ちょっと! ずるいよ、なんで起きないの!」
沈黙のち、獏良が泣き伏せるようにして盗賊王の胸に二度目の頭突きをした。またしても八つ当たりだったが、こうなることを予測していた盗賊王は今度こそ、無様なうめき声を上げたりはしない。代わりにどうしようもない、といった表情で、頭を掻きつつ、
「了が乗っかってっからオレ様動けねえし」
「ボクもバクラに足枕にされてて無理」
「こっちは汚ねぇ足に髪踏まれてんだよ」
見事な三すくみだった。
誰かが少し、ほんの少しの優しさで頑張ったなら何もかもが解決するのに、たっぷりとした事後の気怠さ――では生温い、ただただ重たい疲労が折り重なって爪の先ほどの妥協も出来なくなっている。獏良は寝返りを打てばよく、バクラは頭を少し動かし、盗賊王は足をずらせばそれで済む。それすらしたくない、もう自分の為以外のことは一切したくない。
三人が三人、文句を同時に言おうとして、止めた。
そうしてより一層脱力し、深い溜息のトリオが響く。
窓の曇りはいくらか晴れ、それはそれは美しい秋空が覗いているのがかえって恨めしい。一体何をやっているのか。
「あーあー、しまらねえなぁオイ」
代表して総意を述べた盗賊王が、ぱたん。
太い筋肉のついた褐色の腕をぞんざいにベッドへ捨てる。その動きが出来るなら足を退かせるはずだが、もうその話は終わっているのである。
「さっきまでしっぽりだったのによォ、何だこりゃあ」
そう、これは事後なのだ。本来ならば一番とっぷりとっくり、疲労に身をゆだねつつ余韻に浸るところである。なのにこれでは、先ほどまでの情事は夢か何かだったのではないかと疑ってしまうのも無理はない。
盗賊王は回想する。あられもなく両足を開き、この身の上に跨って高い声を上げていた獏良は幻だったのか。細い身体を震わせながら自立もままなならない腰を支えてやりつつ、下手糞な口淫で頬から喉までをいやらしい汁で汚していたあの光景は白昼夢か。あとついでに、口で頑張る獏良を容赦なく背後から責め立て哂っていた嗜虐の塊のような、ぎらぎらした目で獏良を犯しつくしていたバクラも。
あの性質の悪い麻薬のような、怠惰で濁った極彩の宴はどこへ行ってしまったのか。現在も確かに多大に怠惰であるが、湿っているのは肌だけで、官能はすっかり蚊帳の外だ。盗賊王だけでなく、全員がそう感じていた。
何とも言えない、気まずいような腹立たしいような沈黙が続く。
「いっそもう一戦やって、全部有耶無耶にしちまうってのはどうだ?」
そんなやぶれかぶれの提案まで出てきてしまうくらい、状況はイエロー。どうにもならない五里霧中だ。
どうせ何を持ちかけたところで文句と否定しか返ってこないに決まっている。そう決まりをつけて戯れに口走った盗賊王だったが――
「……てめえがその場所代わるならな」
あにはからんや。バクラが乗ってきた。
おいマジかよ、とうっかり言いそうになるが、ここで遮っても面白くない。視線だけで伺うと、バクラは少し回復したらしく、肘を獏良の脛の上に付いてねめつけるような眼で盗賊王を見ていた。
「テメエが一番楽な場所に居んだろうが。ソコ代わって宿主サマが頑張って下さるなら、考えてやってもいい」
「うわ、それマグロっていうんでしょ。狡くない?」
「貧血に腰振れっつうのかよ。ひでえ話だ」
「もうこの際だ、オレ様は構わねえけど、了どうするよ?」
どうする、などと問いながら、ノーと言わせる気は全くない。思い通りにしないと気のすまない男は、ベッドの上でもオレ様だった。
否定させない視線はくるりと獏良のもとへ。伺いつつ薄い期待の下心が滴る青と紫に睨まれると、獏良は弱い。疲れ切ってもう何の反応も起こさせないはずの場所がきゅんと疼く感覚に、咄嗟に息を吐いてしまったらもう駄目だ。目ざとい彼らには全て見透かされている。
「……動きたくないんじゃ、なかったの」
せめてもの反抗に、顎を引いて小さく呟いたなら、すぐに頬をすくわれ上向かされた。皮膚の厚い掌に薄い頬を摩られ、そりゃあなァ、と盗賊王は唇の端を持ち上げる。
「腹も減ったし疲れてっし、動きたくねえさ。だから了が頑張んだろ?」
「何それ、ボクだってしないよ……」
「どうだかな、宿主サマは我慢が苦手でいらっしゃる」
するり。脛から膝の裏にかけて、バクラの骨ばった手指が這う。敏感な個所を通り過ぎる指は微かにまだ湿って、昼過ぎの狂乱を思い出すには余りある。
「始まっちまったら、宿主サマはちゃあんと踊って下さるさ。特等席で見せて頂くのも悪かねえ」
するり、するする。ゆっくりと身体ごと這い上がってくるバクラはまるで蛇のようだ。いつの間にか獏良はがっちりと左右を固められ、逃げ出すにもどうにもならないがんじがらめになっていた。
この二人が結託すると性質が悪い。普段は仲が悪い癖に、獏良をいいようにする時にだけ、彼らは目配せで囲い込みをしてくるのだ。肩がぶつかるだけでメンチを切り合うこともしばしばあるというのに、今は獏良を挟んで顔を突き合わせても文句さえ言わない。
つまりは目的の為に手段を択ばない連中であり、そして、獏良の勝率は今の所全敗なのであった。
「こ、ういう時だけ、卑怯だ」
「何とでも」
「あァ、コッチも随分その気になってるみてえだし、な」
不穏な動きで、盗賊王の手が獏良の腰を撫ぜる。肉のない尻は無視し、その先にある熟れた場所を目指して悪戯な指が進軍開始。ひくんと跳ねた所で、耳朶を噛まれる。
「生肉でもいいから食え、っつったのは了だったよなァ?」
力の入らない手指を絡め取り、バクラは指と指の間の柔らかい部分に、それこそ蛇のように舌を這わせる。辿って辿って先まで到達、指の腹に舌先を押し付け、たっぷりと唾液を絡めて舐り尽くす。
「夕飯もデリバリーでいいなら、後の事考える必要もねえし」
「や、ちょっ、ほ、本気?」
「冗談だったら良かったです、ってか? 生憎マジだぜ、グダグダんなっちまってンだから、きちっと締めようや」
熱い吐息が耳孔を犯して、反射の身震い。
あう、と情けない声が上がったら、事実上の白旗だった。
「無理だってば、動けないよ! こ、腰とか、重たくて」
「今更なんだよ。入っちまえば勝手に動くって。さっきだって凄かったじゃねえか」
「あんなテクどこで覚えてきやがった? 自前だったら大したモンだ」
目を閉じてしまうと、良く似た声の二人のどちらがどちらを喋っているのか獏良には解らなくなる。いずれにせよどちらが発した言葉でも意味合いはそう変わらず、そうしてこれから起こることにも変わりもなかった。
そうして何より、その起こる事に――少しだけ、熾火のような危うい期待を感じてしまっているからこそ、獏良は抗いきれない。
動きたくない、だるい、寝ていたい、お腹すいた、二人とも勝手すぎる。そう訴える自分自身の声が微かに甘い。とっくに受け入れる心持になっている心に身体の疲労が追い付いていないだけで、それこそ今更、だった。
二人に、自分自身に抗って抗って、そうして得るものは何だろうか。そこにはただ停滞した怠惰と空腹があり、嬉しいことは何もない。だったらもう全て投げ出して流れるままに任せてしまった方が楽だ。誰が一番頑張るかなんてことはやってみないと分かりはしない。案外またバクラが負けん気を起こして攻め立ててくるかもしれないし、興が乗った盗賊王が物凄い追い上げを見せてくれるかも。そしてあるいは獏良自身が二人を凌いで乱れに乱れるかもしれない。
そうして得るものは空腹などものともしない、認識すらできない泥沼の快感と、糸がぷつりと切れるように訪れる、失神に似た意識の失墜。それなら何も感じない。目覚めた時のことも、考えたってつまらない。マイナスの皮算用など誰も望まないのだ。
「……じゃあいっそ、酷くしてよ」
しばしの沈黙の後、折れた獏良の呟きに、バクラがにやりと笑う。
「そりゃあこっちの台詞だ」
手酷く搾り取ってくれよ、宿主サマ?
バクラの、まるで滴るような言葉が事実上の幕開け。
それぞれがそれぞれに伸びる官能の手指はまるで触手だ。ひたりと触れればそこからじわり、いやらしい何かが染み出て感染する。そうして一個体の、ひとつの快楽の塊になってしまえば、もう何も――
――ピンポーン
「シュークリーム!」
疲労、官能、空腹。
全てがシュークリームによって圧倒された瞬間だった。
窓の向こうは既に空は黄昏を引きずった紫に染まり、夏が終わり日が落ちるのも早くなった時刻はそう、丁度午後七時の色をしていた。勤勉なる宅配便の配達員は、この六〇一号室に予定どおりの時間内でもって最速で、獏良が取り寄せていたという絶品生クリームとろふわシュークリーム三個入りを届けにチャイムを鳴らしたのである。
全てを凌駕し、瞳孔がシュークリームの形に変わった獏良が勢いよく起き上がった時、まず旋毛が牙顎――盗賊王の顎先端を襲った。瞬間的な衝撃によって打ちどころが悪ければ脳震盪をも起こすという人体急所に突如向けられた攻撃に、油断していた盗賊王は反応しきれなかった。舌を噛まなかったのは幸いである。しかし、「ふべっ」という、長い人生の中で大凡発したことのない奇天烈なうめき声をあげた彼はそのまま物理法則に従い、枕に昏倒した。
その時、長い髪が災いを呼んだ。
バクラの髪の先端が倒れた盗賊王の腕に巻き込まれ、引っ張られて頭の位置が固定された。そこへ襲い来る、飛び起きてベッドを下りるべく振りかざした獏良の細腕がまさにクリーンヒット。これもまた人体急所の一つである鼻の下、人中へと叩きつけられる無意識の攻撃に、バクラもまた「ほばっ」と、元闇そのものが上げてはいけないみっともない声と共に崩れ落ちた。いくら細い腕とはいえ、遠心力が加わればちょっとした棍棒ほどの衝撃となる。鼻血が出なかったことが幸いだった。
「ちょっ、はーい! 今出ます!」
悶え苦しむ二人に目もくれず、痛む腰にも怯まず。獏良はベッドを飛び降り、二回目のチャイムに向けて大声で応じている。
と、そこでようやく己が起こした惨状に気付いたか、振り向いた獏良は転がる盗賊王とバクラに手を掛ける。そして、
「じゃま!」
一声に、二人の下敷きになっているジーンズとTシャツを、テーブルクロス抜きでもするかのように奪い取った。
悲しい事に獏良はマジシャンではない。テーブルの食器ならぬベッドの上の男たちは傷む身体に鞭を打つかのようにすっ転ばされ、一人はベッドを沿わせた壁に激突。もう一人は床に落ちた。
そうしてばたばたと足音が遠のき、ばたん。
「……」
「……」
言葉も出ない二人である。
物理的な痛みは時が経てば落ち着いていく。玄関を開く獏良の賑やかな声が遠く聞こえるのを聞かされているうちに痛みは痺れとなっていったが、それよりも二人を打ちのめしたのは精神的なそれであった。
シュークリームに負けました。
などと、プライドが許さない。
否、獏良了という少年が一種のファンダメンタリスト、異常とも表現して差し支えないシュークリーム原理主義者だということは理解している。ただ人として、肉欲とは抗いきれぬものであり、二人が仮のお誘いに負けることなどないと思っていたのだ。
それを容易く裏切られ、しかも無意識とはいえ暴行まで受けた二人の傷は深い。なんだかちょっと泣きたくなってくるくらいに衝撃だった。食べ物に負けるなどと、あっていいことではない。
あるいはこれがバチというものなのだろうか。
二人がかりでその気でなかった獏良を焚き付け、火をつけ、うまいこと引っ張り上げて乗ってもらってあとはマグロになってやろうというその思惑に対する罰であろうか。身体の負担は皆同じと言いながら、内側から内臓を苛められ、しかも二人分の欲を受け止める獏良に対するあり方が間違っていたと神は言うのか。
いや、神などくそくらえだ。少なくとも彼らにとっては。
「……あんまりじゃねえか、なァ」
呆然、痛み、反省。
そして最後に、やっぱり腑に落ちなかった。
「なあおい兄弟、こりゃあねえよな、あっていい訳がねえ」
「その呼び方止めろっつってんだろ。……だが確かに納得いかねえ、宿主サマにゃあキッツイ躾が必要のようだ」
完治していない貧血に頭をグラグラさせながら、バクラは叩きつけられた壁からずるり、起き上がる。頭から床へ落ちた盗賊王はそのまま前転する形で起き上がり、すっかり汗が冷えてしまった首を掌で摩る。まだ痛むらしい。
扉の向こうでは、獏良がそれはもう上機嫌で、配達員にお疲れ様ですと挨拶をし玄関の扉を閉めたところだ。
目にせずとも目に浮かぶ。冷えてもまだ湿った髪を翻し、踊る足取りでクール便の箱を抱き廊下を歩いてくる獏良の姿。ぺたぺたと裸足のまま、紅茶でも入れてダイニングテーブルで、空腹と糖分欲を満たすつもりなのだろう。
ここに同じく栄養が枯渇した同居人が二人いるというのに。
牙顎と人中を打った相手のことなどすっかり忘れて一人だけ美味しい思いをしようなど、そうはいかない。
「今夜ばかりは手を組もうぜ。寝かさねえ、どころじゃねえ」
「飯も菓子も食えねえくらい、腹いっぱいにしてやろうじゃねえか――たっぷりご奉仕させてやんよ」
パン、と、手と手を打ち合わせたバクラと盗賊王が、ゆらり、鬼の如く立ち上がる。
何も知らず、ダイニングで暢気にいただきまーす、などと手を合わせている獏良とは全く対極だ。
やおら獏良の細い肩に、首に、背中に、二つ鬼のの影がのしかかる。
夜空の雲間から顔を出した丸い月がにやりと笑う。突き抜ける月光を浴びた盗賊王とバクラの姿は、とても先ほどまで怠惰に浸っていたとは思えぬ程、精力漲るそれであった。