【同人再録】アラート-1
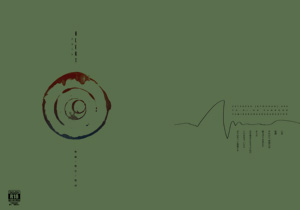
発行: 2013/05/03
■バク獏♀双子パラレル要素あり
双子のバクラと良好な関係でもって生活する宿主。しかしある朝を境に、自分の記憶に違和感が芽生え始める。バクラについての記憶があいまいになるにつれ、不安は増大し――みたいな、全体的に薄暗い話。
心音 暗闇
それから、時間の音
眠るボクを 急かす
そうだ
目を覚まさなきゃ はやく
だめだ
このままで、いたら
――ボクはきっと 後悔 す る
8:00
そうして、獏良了は目を開いた。
「……あれ」
掠れた声は遠く聞こえ、自分の口から発されたものだと気が付くのに随分と時間がかかった。
声、どころか、全てのものが遠く感じた。
立っているのか座っているのか寝そべっているのか、それすら判別できない。重たく感じて俯かせた頭につられて視線が下方へ向かい、そこで拾い上げた映像が視神経を伝わっていく。それが爪先だったことで、了は漸く、ああボクはいま立っているんだ、と気づけたほどだ。
学生靴の爪先と、紺色の靴下。続く痩せた膝と白い腿。スカート。手のひらは片方が冷たく、片方が温い。冷たい包囲はひたりと壁に手をついて――否、壁ではなくこれは扉だ。玄関の扉。自宅の、玄関だ。温い右手には鞄。そしてポケットでは小さな電子音がアラームを響かせていた。
ぬるい水から上がった後の倦怠感。それとよく似た気分のまま、了は制服のポケットから携帯電話を取り出して見る。午前八時丁度を知らせる、そのアラームを切ろうと操作してみるが何故か音を止められない。ぼんやりと画面を眺め、
(まあいいや)
そんな適当な、胡乱な気分だった。了は小さく首を傾げる。
「それで……なんだっけ」
何をしていたんだっけ。
了は傾げた首を左右にゆるく二回振り、ひっかかる思考を振るってみた。
確か暗闇で、心音が聞こえて。それから時計の音もしていて。
何だかとても焦っていて、目を覚まさないといけないと思った。
でないと、
(後悔?)
する、と。
そして目を開いたのだ。
そうしたら、なんだか有耶無耶な気分でここに立っていた。
自分の五識を信じるなら、獏良了はこれから学校に行くところだ。靴も鞄もそう物語っている。振り向けばリビングの掃き出し窓の向こうは朝方特有の、絵の具の青を水で溶いたような色の空が広がり、耳を澄ませば車の駆動音が聞こえてくる。
ありふれた平和な日常の隅っこ。
そこに自分がいることを了は実感する。後悔など、別にしていない。
「立ったまま二度寝してたかな……」
結局、了は一番あり得そうな可能性を正しいと見立てることにした。
まじまじ見る携帯電話はまだ喧しく時刻を主張している。このアラームも設定した記憶はないが、もともと自分は少しぼうっとしたところがあるから忘れているだけだろう。或いは設定をし間違えたとか、そんな取るに足らないことが原因に決まっている。先程は何故か切れなかったけれど、きちんと意識して操作すれば、手癖で出来るくらいに簡単にアラームを停止できた。
と、鳴りやんだ瞬間に、今度は玄関扉から音がした。
「っわ!」
驚いた了が鞄を取り落とす。チャイムではない、そう、まるで誰かが向こうで力任せに扉を殴るか蹴るかしたような音だ。ガンガン、と二回、繰り返してそれから静かになる。
そして、微かに舌打ちが聞こえたかと思うと、施錠された鍵がいきなり開いた。
「わ、わ、わっ」
思わずドアノブを掴むと、扉向こうの気配も一度制止した。今度は控えめではない、ひどく不愉快そうな大きな舌打ちが響く。その音はまるで咎めるようで、了は反射で手を離してしまった。
対抗する力がなくなったことで、ドアノブは勢いよく下がる。扉を押しとどめることもできず開いたそこにいたのは、不機嫌な表情をした男だった。
男は了を見、足元に所在なく墜落したままの鞄を、腰を折って拾い上げた。そして、
「なにやってんだよ。そこにいんならてめえで鍵くらい開けろ」
開口一番文句を云った。
言葉に詰まった了はぽかんと男を見上げる他ない。彼は――よく知っている男だ。白く長い髪も白い肌も、眇めた青い瞳も、学生服姿で少し猫背気味に立つ姿も。先程の携帯電話のアラームを切る時と同じ、身体に染みついた存在。
そうだこれは、
「バクラだ」
「あァ?」
当たり前のことを口に出したら、不機嫌の上に怪訝を上塗りした声で返されてしまった。
そう、バクラだ。これはバクラだ。
「八時つったのはソッチだろ。まだ寝ぼけてんのか?」
「え、や、どうだろ。ちょっとぼやっとしてるかも。元気だけど」
「元気かどうかは聞いてねえよ。更にどうでもいい」
悪態は不愉快さを生まず、何故かかえって安心できた。
自分と世界の間にある薄膜から、バクラに手を引かれて抜け出した気分だ。正体不明の違和感の海から顔をあげ、漸く息を吐き出せた感覚。引かれるように踏み出した足がバクラの学生靴の脇に辿り着き、了はスカートを翻してマンションの廊下に出た。
朝方の透明な空気を吸い込み、深呼吸。頭の中が少し冴える。
緩んだ脳は漸く、了の中の違和感を片づけるために働き始めた。ここは自分の家で、これから学校へ行く。一時間目は数学で小テストがある。昼休みは友達の皆と屋上で食べる予定で、帰りにスーパーに寄って特売の白菜を買って、夕飯は鍋。昨日決めた予定もきちんと思い出せる。そう、そして、バクラは――
(バクラは?)
何故か、バクラのことだけが上手く思い出せなかった。
振りむいた了はバクラを凝視する。見慣れているのに何か違う気がする彼は、どういった人間だっただろうか。意地悪いことを云って、性格が悪くて、そういうことは分かるのに、どこからどう見てもバクラなのに、了には目の前の男がバクラであることに自信が持てなかった。
「バクラ、だよね?」
「はァ?」
「なんか変だ。バクラがバクラじゃない気がする」
「何だそりゃあ」
問いかけたなら、バクラは心底意味が分からないという様子で溜息を吐いた。
それから面倒くさそうに手が伸び、頭をぐしゃぐしゃにかき混ぜられた。最後にぽんと叩いて、腕を引かれて歩き出す。
「歩いてりゃ目も覚めンだろ。とっとと行くぞ」
「う、うん……」
手首を掴む手は冷たかった。ひんやりと心地よい反面、気持ち悪くも感じる。まるでヒトではないような冷たさ――違う、覚えがないのだ、この温度に。
手を引き先を行くバクラの背中を、了は不安な気持ちで見つめた。寝ぼけなら、もう解消している。昨日のことも、一昨日の夕食だって思い出せる。バクラのことだけが薄弱としている。違和感の海から引き揚げてくれたのはバクラなのに、そのバクラが曖昧なのだ。気持ちの悪い齟齬に了は唸り、ねえバクラ、と頼りない声で呼んだ。分からないことは考えるより、質問してしまった方が早い。
「何だよ」
と、その声を聞くと、ああ、そうだこういう声だった、と思うのに。
「バクラ……バクラはさ、えっと、変なこと聞くけど」
「今更だろ、てめえが変なのは」
「うん、今日は自分でも変だって分かってる。わかってるから、ちゃんと答えてね。
バクラは、えっと、一緒に住んでたんじゃなかった、っけ」
「……」
沈黙があった。ごく短い時間だったけれど。
何かまずいことを問うたのかと了は視線で伺ったけれど、首だけで振り向いたバクラの眼には深刻な色合いはひと匙も含まれていなかった。これは呆れだ。それも最大限の。
「てめえがそうしろっつったんじゃねえか」
「へ?」
「一人の時間がないと落ち着かない、絶対無理だ、っつって隣にもうひと部屋取らせたのはてめえだろ。親父に感謝しろよ」
「そう……そうだっけ?」
「そのくせ朝は起こしに来いだの、帰りは一緒だの、訳わかんねえっつうの。双子だからって四六時中ベッタリっつうの、いい加減卒業して欲しいモンだぜ」
云われればそのとおりで、我儘を云ったのは了自身だった。
ひとつ紐解けると思い出す。バクラは双子の兄だ。同じ高校に通っていて、マンションも同じ。もともとは同じ家に住んでいたけれど、不在がちな父に頼み、転校する時に六〇一号室と六〇二号室を二部屋借りてもらった。理由は先程バクラが云ったとおり、一人の時間が欲しかったからだ。正しく表現するなら、自分の都合のいいタイミングで一人になれる空間が欲しかった。だからバクラは家族だけれど、隣の部屋に住んでいる。だけれど行動は大体一緒で、学校に行くのも帰るのも二人だ。食事はたまに別々で、基本的には了が作る。
それから、バクラは了の友人たちとはあまり仲が良くないので、学校に行ってからほとんど接する機会がない。バクラの方が避けるので了も追いかける真似はしない。どうせ帰宅すれば、夕食以降は二人きりなのだ。深夜になれば自然とベッドを共にする。毎晩ではないけれど、結構な頻度で。
(バクラと、ボクは)
家族で、双子で、クラスメイトで、
恋人だ。
誰よりも近くに居る、唯一無二の相手だ。
「――大丈夫か、オイ」
ぴたりと足を止め、バクラは怪訝な声でもって了の思考を遮った。
バクラばかりを見て歩いていた了は気が付いていなかったが、はっと周りを見渡せばここは通学路のど真ん中だ。周りには同じ制服を着た生徒がめいめいの速度で校門を目指している。そんな人の川の最中でバクラは立ち止まり、了を窺っていたのだった。
「寝ぼけてるってレベルじゃねえだろ。変なモンでも食ったか」
「……食べてない」
「だったら風邪でも引いたか」
と、ぺたん。
手首を掴んでいた手が離れ、手のひらが了の額を覆った。
途端、ぞくんと――どくん、と? オノマトペでは表現しきれない正体不明の波が、了の背中を逆さに辿り上げた。
それは悪寒だったのかもしれない。或いは心音の、胸のときめきだったのかもしれない。ただバクラが自分を心配し、同校の生徒が行き交う道の上でそういったことを行ったことに、了はひどく動揺した。
掌は冷たい。熱はねえな、と呟く声は、平素。
人の視線など気にせず触れ合った男は、その手をひらひらさせた後、何でもない様子できびすを返して歩き始めた。
「具合悪ィならとっとと早退しちまえ。てめえがぶっ倒れたりするとオトモダチがオレ様んとこまで来て煩ェんだよ」
「わかった……」
と、まともに答えられたかも危うい。
了は不穏な心臓を手で押さえたまま、小鹿よりも危ない足取りで、ふらふらと登校するほかなかった。
12:18
昼休みを過ぎた頃には、バクラへの違和感以外の気分の悪さは拭い去られていた。
授業の合間にちらちらとバクラの姿を覗き見ていたけれど、特におかしなところはなかった。とりたてて表現することすら難しいほどの普通の姿だ。
彼の授業態度は真面目ではない。至極適当に授業を受け――現国の時間だけは不在だったので大方どこかでサボっていたのだろう――シャーペンをくるくると回して退屈そうだったり、いかにもかったるそうだったりと、そんな程度であった。
四時限目が終わった時、椅子を蹴って立ったバクラが了のところに一度来た。無言で手を差し出されたのでとりあえず握手してみたら、違うだろうと怒られた。昼飯、と云われてから気が付き、勝手に鞄を開けられて、二つあった包みのうち一つを持って彼はさっさとどこかへ去ってしまった。作った覚えは、弁当の包みを見てから思い出した。今朝だけではなく毎日、了はバクラと自分の分の二つの弁当を作っていることを。
入れ違いに訪れた友人たちと、了は穏やかな昼休みを過ごした。
彼らとの会話に何の問題もない。もしかしたら友人にもバクラに感じたような違和を感じるかと心配していたのだけれど、喜ばしいことにそれは杞憂だったようだ。息をするのと同じくらい自然に、笑いあい、共通の話題で盛り上がる。
遊戯と、城之内と、杏子と、本田と。彼らは了が転校してきた時、輪の中に了を迎え、それからずっと、五人組の仲良しグループだ。
「そうだ、今日、獏良くんの家にいってもいい?」
購買の焼きそばパンを小さい口で頑張って頬張っていた遊戯が、屈託ない様子でそう云った。
「昨日城之内くんが云ってたゲーム、皆でやりたいぜーって話してたんだ」
「獏良んちならテレビでけーし、気楽だしよー」
「城之内、あんたが寛ぐのって度が過ぎてるわよ。人の家で靴下まで脱ぐの、いい加減やめなさいよ」
「でも獏良んち、ほんと居心地いいよな」
口々に喋る友人に、了はうん、うん、と頷く。ああ、なんて幸せな時間なんだろうと噛み締めながら。
「獏良くんも、迷惑だったらちゃんと云わなきゃダメよ。こいつら女の子の家だっていうのに、全然気使わないんだから」
「あはは、でも全然構わないよ? ボク一人だし、それに」
それに、バクラは隣の部屋だし。
と、言おうとしたところで、了ははたと箸を止めた。
今日。今日の予定はきちんと覚えている。けれどバクラは、バクラとはどうするのだったかが曖昧だった。
友人は今日の放課後、了の家に来るという。それはとても嬉しいし、遊びに来てもらえることそれ自体が、了にとってはとてつもない喜びだ。何故そんな風に思うのかは分からないのだけれど、友人と共通の時間を過ごせること、家に訪れてくれることが心の底から喜ばしい。できるなら断りたくない。
だが、もしかしたらバクラと何か約束をしていたかもしれない。覚えはないけれど、彼に対してだけ曖昧な記憶では確信が持てない。
『風邪でも引いたか』
登校時に心配してくれたバクラを思うと、胸の奥のあたりがちくりと痛む。
約束がなくても、それでも、バクラといた方が、きっといい。
しばし迷った後、了は些か大袈裟な手振りではあったけれど、友人たちの誘いを断ることを選んだ。
「ごめん。今日はちょっと都合悪いや」
「何だ、またバクラかぁ?」
城之内の口振りが、また、という言葉が刺さる。
「……そんなにボク、バクラ関係のことで皆と遊ばなかったりしたかな」
「つか獏良がオレらと一緒出来ねえ時って、だいたいあいつ系の理由だろ?」
本田が苦笑いで云う。
「ま、しょーがねえよな。彼氏だもんな」
「彼っ……、いや、そうだけど」
「やだ、今更何照れてんの? 今日だって朝、手繋いで歩いてたじゃない」
「見てたの!?」
杏子にまで云われ、了は思わず頬を赤らめた。そしてそんな反応を返した自分に驚いて更に耳まで赤くする始末だ。赤面だなんてそんなこと、するような性格じゃなかったはずなのに。
目に見えて動揺した了へ、遊戯が笑顔のままで更に追い打ちをかけてくる。
「獏良くんって普段飄々としてるけど、バクラくんのことだと結構赤くなったりするよね」
「そ、そうかな」
「女の子なんだから当たり前でしょ。そんなんだからアンタ達、彼女できないのよ」
「ひでぇ!」
大袈裟にがっくりとうなだれる男子三人に、鼻息をふんと鳴らし、形のいい胸を反らせる杏子である。
「大体、顔以外でもアンタ達劣っちゃってること自覚しなさいよ。バクラくんは料理手伝ったり重たい荷物持ってくれたりするらしいじゃない。そういう気遣い、出来る?」
「え、そ、そうだっけ?」
「何云ってるの、獏良くんが云ってたんじゃない。結構優しいんだって惚気てたの、忘れちゃった?」
そう――だった。
やはりバクラ関係のことは抜け落ちている。曖昧に言葉を濁す了の胸の内に、少しだけ落ち着いていた不穏が再びの北風となって吹き始めた。
杏子の話題に乗るまでに、惚気た覚えなど一切なかった。引鉄になってやっと思い当たる。つい最近のことだ。女子だけで遊びに行った時にそんな話をした。バクラが買いもの帰りに重たい方の荷物を無言で持って行ってくれたこと、何だかんだで夕飯の準備を手伝ってくれたこと。勿論、気分よくやってくれているわけではない。毎回やってくれるわけでもない。面倒くさそうに、かったるそうに、文句を云いながらのことだ。だけれどそれでも助けてくれることがあるのだと、珍しくそんな惚気話をした。
ようやっとすらすらと思い出せる。けれどそれは本当にきちんとした記憶だろうか? 相手に云われて知覚しただけの事象は、はたして記憶と呼べるのだろうか。何一つ、自分の体験したことだと断言できないのに。
(ボク、の、頭の中、やっぱりおかしい)
自発的に思い出すことが出来ない。
バクラのことを。
今バクラについて話してくれと云われたら、まともに喋れる自信がない。今朝のことなら分かるけれど、それ以外の記憶が曖昧すぎて、語る言葉を紡げない。そのことを深く実感した了は、遅まきながら恐怖を感じた。おかしいのだ、絶対に、何かが違う。間違っている。
――かち、こち
「――今の音、何?」
「音?」
会話を遮る形で呟いた了に、全員の視線が集中した。
複数の視線の真ん中に晒されて、了は少しばかり居心地の悪い心持を味わった。
「今、何か音がした。時計の音みたいな」
「そうかぁ?」
「ボクは聞こえなかったけど」
皆は気づかなかったらしい。了の鼓膜を叩いた音――時計の秒針が働く時の、チクタクと、かちこちと、一定のリズムで刻まれる音を。
耳を澄ませてみる。ところがもう、了の耳にも拾えない。
「気のせいかな……」
まるで急かすような、そんな風に聞こえた音だったのだけれど。
いずれにしても引っ張るような話題でもない。本物の時の音――昼休みの終了を告げる鐘が鳴ったことで、了たちはめいめいの荷物を持ち、屋上を後にした。