【同人再録】ヤドリギの果-1
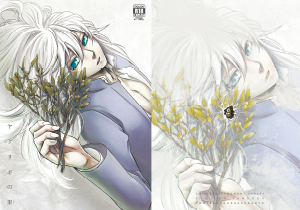
発行: 2014/12/28
サイト公開中の【Etreinte.】の再録とその続編になります。このページには続編のみ掲載です。
最終回後、異形の姿で宿主の心の部屋に帰って来たバクラとそれを守ろうとする宿主のお話。
救われない系バッドエンドです。
・小説:書き下ろし
・表紙:半田96様
※若干のグロテスク要素が含まれています。ご注意ください。
自分の心の奥底への道など、普通ならば誰も知らない。
自らの足で行きつけないからこそままならないのであって、そうしてそこへ行きつけたところで、コントロールなどできない。心を意のままに出来たなら人々はどれほど安楽に生きて行けるだろう。言葉と本音は彼岸と此岸に隔たれている。
その道を、隔てる川を往ける小舟を、かつてはバクラが漕いでいた。
いつだってバクラに手を引かれ、導かれ、獏良は自分の心の中へと連れて行かれた。掌で生ぬるい目隠しをされた盲目の世界では体温だけが手がかりで、彼がときたま纏わせる砂の匂いを頼りに、川を渡った。
今。
手を引き、船を漕ぐ者がいなくなって、そこへ――心の部屋へ向かうのは難しい。
それは命がけの手さぐりだった。ひとつ道を間違えたら永遠に現実に戻れないかもしれない。背中にひやりと伝う恐怖に足がすくむこともある。息を止め続けて深く水中を泳いでいるのだ。今水を掻いて浮上すればまだ間に合う。息の続くうちに戻れる保証はどこにもない。判断を間違えたら、この闇にどこまでも沈んで行ってしまう。
引き返そうか。
怯える度に、微か遠くから砂の匂いを感じた。
微かに混じって、生々しい鉄錆の匂いも。
(そうだ、だいじょうぶだ)
目隠しなんていつものことだ。引く手は無くてもこの匂いを覚えている。血の匂いは、今のバクラの姿をありありと思い出させて引き返す気を押し込めた。あの傷だらけの存在を放置できない。
放っていたら、また居なくなってしまいそうで。
恐怖に打ち勝つのは別の恐怖だった。唇をかみしめ、そうして獏良は深い川を渡るのだ。
力任せに泳ぎ、やがて伸ばした手が岸に触れる。大きく吐き出す息とともに水面に上がる、そんな感覚だった。ずっと瞑ったままだった瞳を開ければ、そこにはなじんだ景色があった。
三十五・七度の生温い暗闇に浮かぶ、扉。
獏良の心の一番奥の部屋の扉だ。
乱れた息を整えて、見慣れた自室の扉を象ったそれの、ドアノブを掴んで回す。鍵は掛かっていない。音もなく開く向こうはやはり真っ暗で、此処はいつでも視覚が役に立たない場所だった。
盲目には慣れている。微かな砂の匂いを辿ればいい。
耳を澄ませれば痛々しい呼吸の音が、肌を擦れば他人の気配が伝わる。
「バクラ」
唇を湿らせてから小さな声で呼ぶと、呼吸がぜひゅう、と、返事するように乱れた。
どこかではなくここに、バクラは居た。
そっと手を伸ばすと、乾いた髪に触れた。さっと頭が逃げる。
「ただいま、バクラ」
相変わらず形がどうなっているのか――人の形をしているかどうかも分からない、それでも確かにバクラであるそれの隣に、獏良はすとんと腰を下ろした。
眠る前の、命がけの逢瀬だった。
高校生としての普通の生活――朝目覚め、学校へ行き、食事をして、家事をして、宿題をして風呂も済ませ、ベッドに潜り込んだ後。
夜と朝の間だけ、獏良は「普通」の向こう側へと向かった。自分の心の奥底へ沈み、ほんの束の間、そこでしか会えない男に、会いに行くのだ。
バクラ、に。
きっと異形の姿をしている、彼に。
「ちょっと遅くなっちゃったね」
掌ひとつ分をあけて隣り合い、獏良は普段どおりの口調で語りかけた。
「今日はね、ちょっと面白いことがあったよ。城之内くんが他のクラスの子に告白されたんだって。初めてだってさ」
「皆大騒ぎになっちゃって。それで帰りにバーガーワールドで長居しちゃった」
「それでここに来るの、遅くなっちゃったんだ。ごめんね」
つるつるつる、と、言葉はとめどなく溢れてくる。今日あった出来事をもの言わぬバクラに報告していく。
バクラは返事をしなかった。ただ何となく、こちらの話を聞いている気配はあった。あまり近づくと威嚇されてしまうから、近づきすぎない手のひらひとつ分の距離を保って、獏良は話す。
こんな話をしても、聞いている方は楽しくないかもしれない。否、もしかしたら話を理解することも、出来なくなっているかもしれない。今のバクラにバクラとしての自我があるのか、調べる術はどこにもなかった。ただ初めてここで再会した時流した、ぬるい涙だけが彼を彼足らしめている。
言葉を話せず、纏っていた闇を引きはがされ、ちっぽけなかたまりになり、さらにその一欠片――その程度の、とてもいびつな存在になったのだろうと、獏良は思う。
バクラと遊戯と、仲間たちと。
その戦いの中で起こった全てのことを、獏良は把握していない。こういうことがあったのだと説明を受けても、その場にいなかった獏良にとっては夢物語に等しい、どこか遠い誰かの話でしかなかった。さらにそこでは語られていない、バクラが何を思い、どうしてこうなったのかなど、知る方法すらなかった。
ここには結末と、結末からの少しの続きだけが息をしている。
バクラが一欠片だけでもいい、ここへ帰って来たこと。
それだけが全てで、答だった。
「――ねえ、バクラ」
抱えた膝に額を押し付け、獏良は言う。
「どうして誰も、お前のことをわかろうとしなかったんだろうね」
それは、自分自身にとっても茨として返ってくる言葉でもあった。
「そりゃあボクだって最初はお前のこと、何も知らなかったけど。教えてもくれなかったし、何よりお前自身が語りたがらなかったからかな。
同情も同調もされたくなかった? 誰とも居る気はなかった? それでもボクは知りたかったよ、ずっと」
相槌のない言葉は心の部屋に雪のように積もっては消えていく。泣きだしそうな声だと、自分自身でも思った。
「お前はさ、たぶん、今までずっと一人で生きてきて――誰にも頼らないで、目的の為に頑張ってきたんだろうね。
それが悪いことをする為だっていうのは聞いたよ。でもさ、悪かろうが善かろうが、お前が一人ぼっちで戦ってきたっていうのは本当のことだと思うんだ。ボクにとっては結果じゃなくて、そっちの方がずっと大事なんだよ」
話してくれたらよかったのに、と、呟く。
獏良が一日の出来事をここで語るように、とりとめもなく、バクラがバクラのことを喋って欲しかった。知りたかった、近づきたかった――巻き込んでほしかったのだ、中途半端にではなく、しっかりと絡め取って、逃げられない程に縛り付けて欲しかった。
「お前はボクを置いて行ったよね。それに関してはそりゃあもうボクは怒って、腹が立って……これだけ勝手なことをしておいて、結局共犯者にすらしてくれなかったお前を憎んだよ。帰って来たから、もうそんなこと、どうだっていいんだけど――
お前は負けてしまって、消え去りそうなときにボクのことを考えたのかな。あの時ね、ボクは確かに見たんだよ」
疵の残る左手をかざしてみる。
心の部屋に天も地もないけれど、獏良にとってはそちらが空だった。
目を閉じると思い出す。バクラに置いて行かれ、隔離されていたときのこと。目覚める前に見たまぼろしを覚えていた。
暗雲を払う痛いほどの暁光。雲間から豪雨のように降り注ぐ光の槍。容赦の無い雨がバクラの上に降り注ぎ、彼を貫き身を削っていく。血を流し絶叫し、千切れてゆくバクラは逃げようと身を捩り、けれど逃げ込む先は全て閉ざされていた。
噴き出す鮮血のせいだろうか、纏っていた外套が黒から赤に変わり、ずたぼろになって、長い髪も焼き切れた。片目を十と一に貫く赤い傷が痛々しい。
そして最後に逃げ込んだ場所は、此処。
「お前が居心地がいいって言った場所だもんね」
まぼろしではなかったのだと、今は思う。
宿主として繋がれたささやかな因果が鎖となって垣間見せた彼の戦いの最終幕は、瞼に焼き付いて離れない。
細切れにされてゆく姿は哀れと言うほかなかった。そう思われることがバクラにとって屈辱だったとしても、みすぼらしく傷ついた彼を自分以外の誰が抱きしめてやれるだろう。
「お前を可哀相って思うことを、許してよ」
忌々しい光のまぼろしをかざした手で払って、獏良はバクラに向き直る。
滲むような笑顔を浮かべて、見つめて。
「そしたら、ボクも許したげる。今までお前がしたひどいこと……嘘をついたこと、身体を好き勝手にしたこと、友達を騙したこと、置いて行ったこと、ぜんぶ」
笑みを浮かべた獏良をバクラが覗っているような、そんな気配があった。何故だろう、今は少し、辺りの暗さが薄まって見える。輪郭がほんの少し透けて見えているような、しかし容の全てを辿れない、現実の暗闇で目が慣れた時程度の違いだったけれど。
濃度を変えた闇の向こうで、バクラは警戒するように唸った。
あの時のように抱きしめたい。大事にしてあげたいと、そう思った。
たぶんバクラは知らないのだ、人の抱擁がどれだけ暖かいか、手をつなぐことでどれくらい安心するのか。獏良自身も忘れていたことだけれど、幼い頃――まだ妹が生きていた時、家族という暖かさを確かに経験している。
かつてバクラに与えられた肉欲や欲望の満足とは違った形の、もっと暖かな接触も存在することを、教えてあげたい。
「バクラ」
手を伸ばすと逃げられた。掌一つ分だった距離が足にして三歩分くらい開いてしまった。這って逃げた跡は血がべったりと擦れているだろう。彼の傷はいつだって癒えないまま、新鮮な血を流しているのだ。
「バクラ、今すぐじゃなくていいんだ、ちゃんと聞いて」
これ以上近寄るのは得策ではない。獏良は追いかけようと膝と手をついた姿勢のまま、ぐっと拳を握った。焦っては駄目だ。また、いなくなってしまったら。
「ボクら一人じゃなくて、二人になろう。これからゆっくり……ここにずっといていいって言ったの、本当なんだ、嘘じゃない」
バクラが唸っている。真っ赤に染まった外套にいびつな身体を隠して、言い募る獏良を睨んでいる。
睨む目の本意はつかめなかった。
完璧な拒絶ならもっと遠くに逃げるだろうと思った。しかし手の届かない位置でこちらを覗う視線に手さぐりを感じる。見極めようとする意思。まるで、本当はそちらに行きたいのだけれど不安がっている――
知らないものを見せられて、警戒している獣。
あるいは、優しさに身を寄せることが、信じることが怖くて、怯えているような。
そういった酷く哀れで悲しい生き物に見えた。獏良は苦悩の息を吐く。どうしたら、伝わるだろう。
晒せるものは本心しかなかった。もともとここでは嘘をつけない。今吐き出している言葉がそのまま、獏良の心の底からの想いそのもの――バクラにも、それは分かって居るはずなのだ。
故に獏良は必死に叫ぶ。どうか伝わって欲しいと、願いを込めて。
「お前が前にどんなことをしたかとか、それを咎める人もいない。
お前に居て欲しいって思ってるボクしかいないんだよ。だから、もう大丈夫だから!」
だから――だから。
闇の濃度がまた変わっていく。バクラが慄いたような声を上げてまた一つ向こうへ後ずさっていく気配がした。驚いたのは獏良も同じだった。
どうして急に。
いままでずっと真っ暗だったのに。
「逃げないで、バクラ!」
立ち上がり、追いかけようと一歩踏み込む。いつの間に泣いていたのだろう、頬を零れた涙が暗闇に散って、それが――蛍に似た白い光を帯びて、辺りを微かに照らした。
光を目にしたバクラは呻き、丸まって唸り続ける。
これ以上近づくことは躊躇われて、獏良はただ立ち尽くすしかなかった。
「どうして……?」
ぽたり。また一つ、雫が零れる。
闇の中で異物めく、小さくて明るい粒。
居心地がいいはずの暗闇に浮かぶ涙は、バクラを貫いた光の槍とよく似た輝きを放っていた。